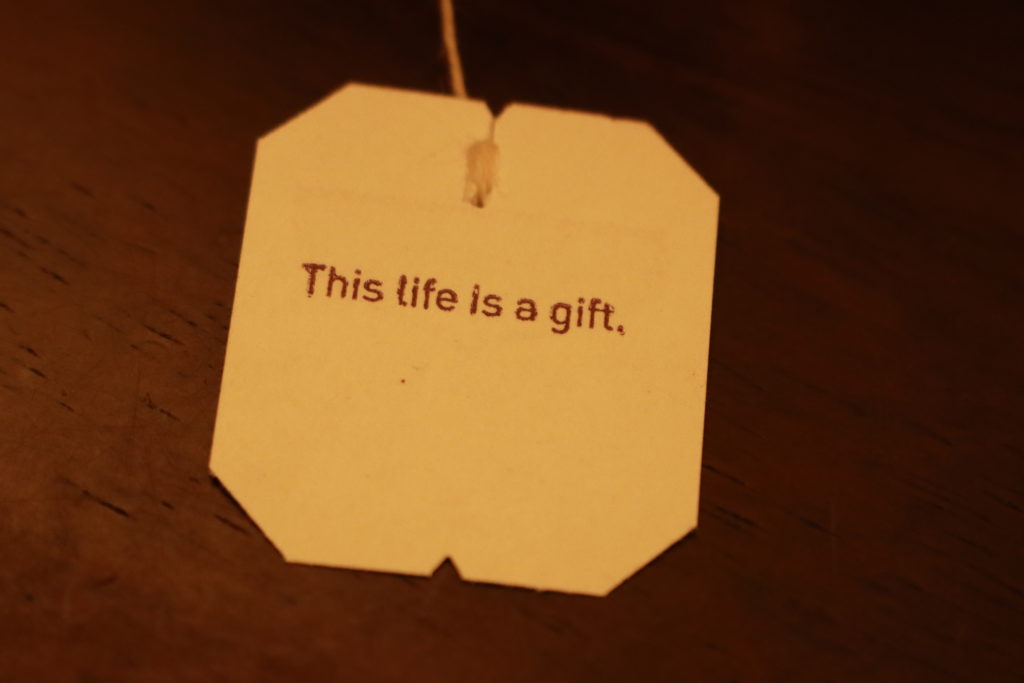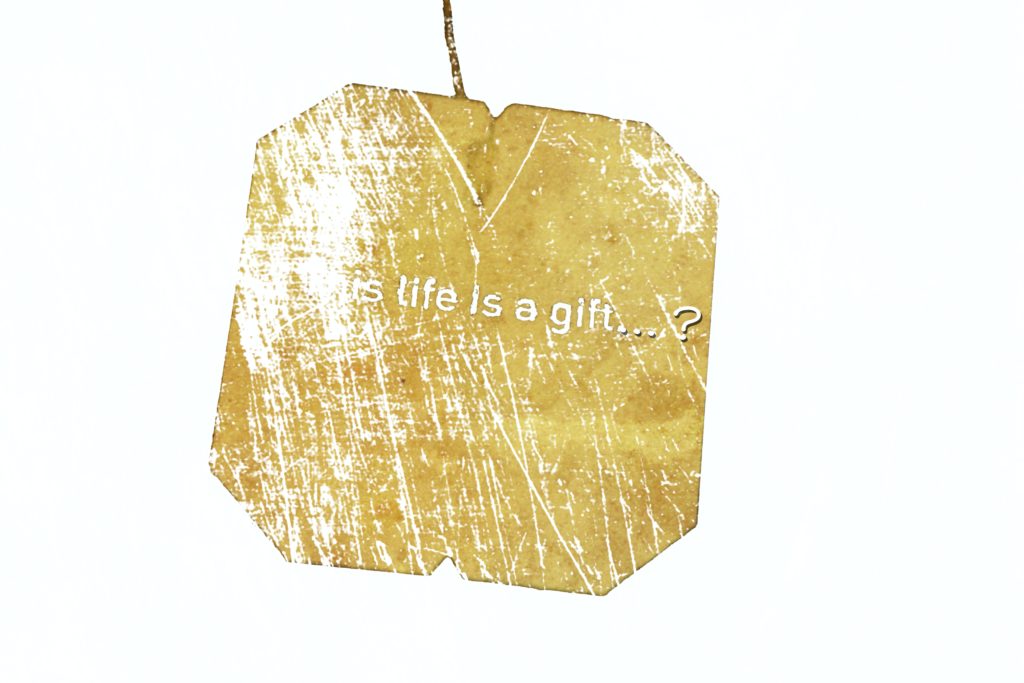2021-05-03

そこに流れていた時間と、
過ごした時間の調和がとても心地よく、
ありがたく…

澄んだ空気と
闇夜の雨音に心が洗われました。
誘いに乗ってくれた友に感謝。
新緑を愛でに…の思いを
完全に体現していた木が1本。
かなわないなー

そしてこちら、
木に差し込んだネジをクルクル回すと
鳥の鳴き声がするBird Call。
効果があるのかもともとなのか、
ちょっとだけコーラスの仲間入り。

記憶の新しいうちに
残像を留めておきたくて、
こちらでちょこっと、おすそわけ。
(※音付きです)
残りの日々もゆるやかに
過ごせますように
yuko / כלב