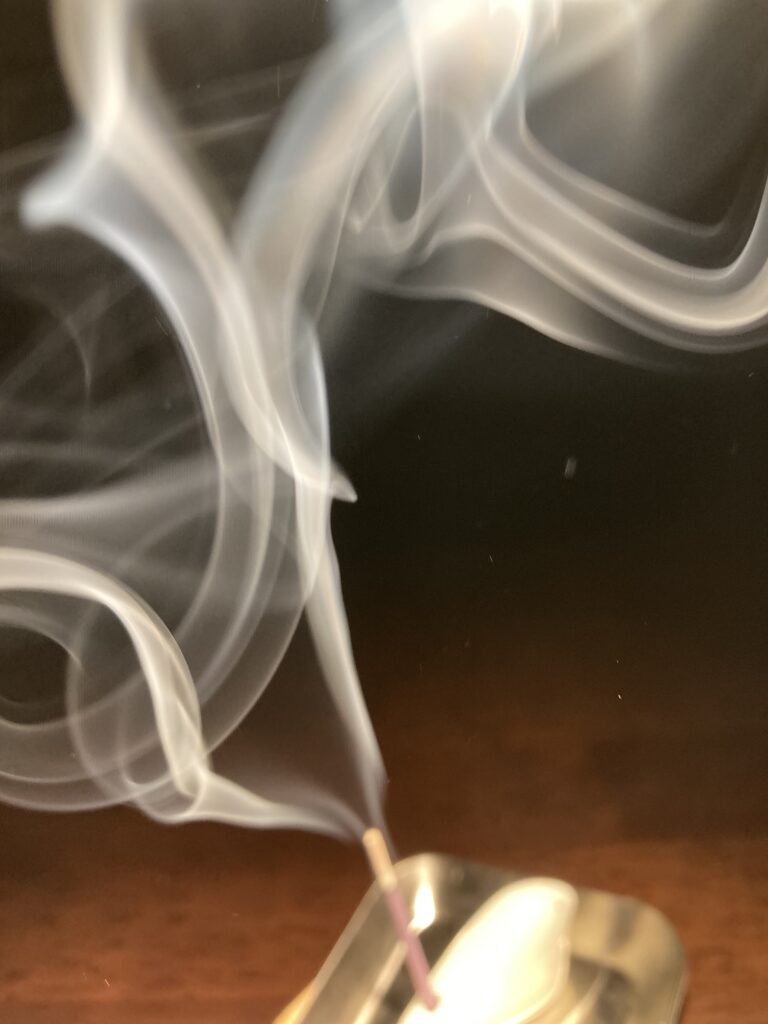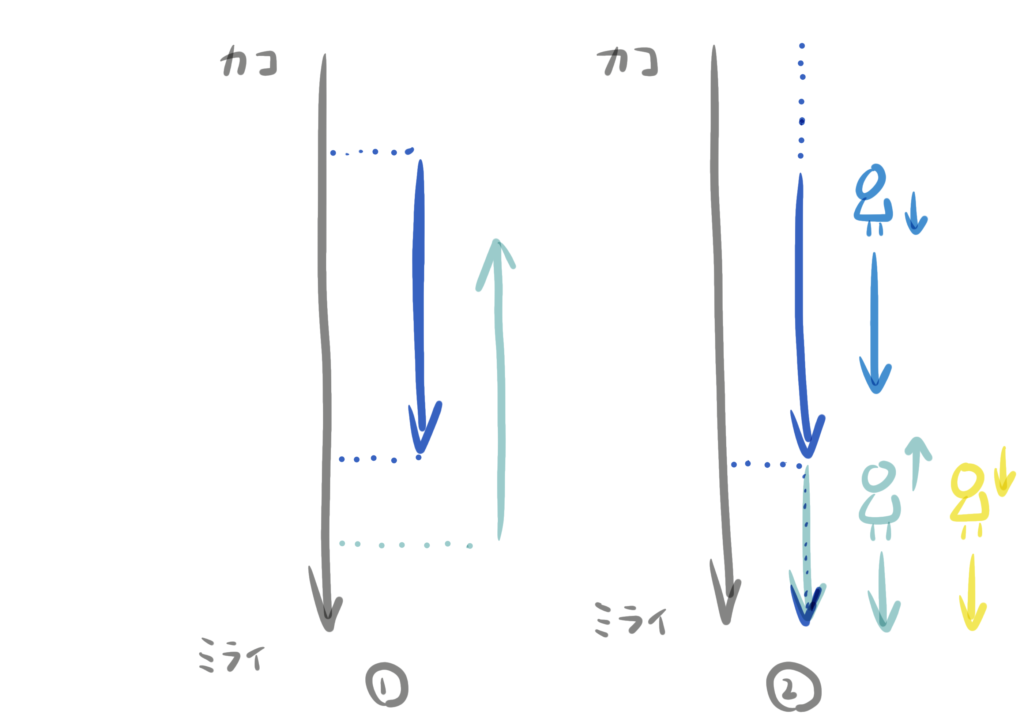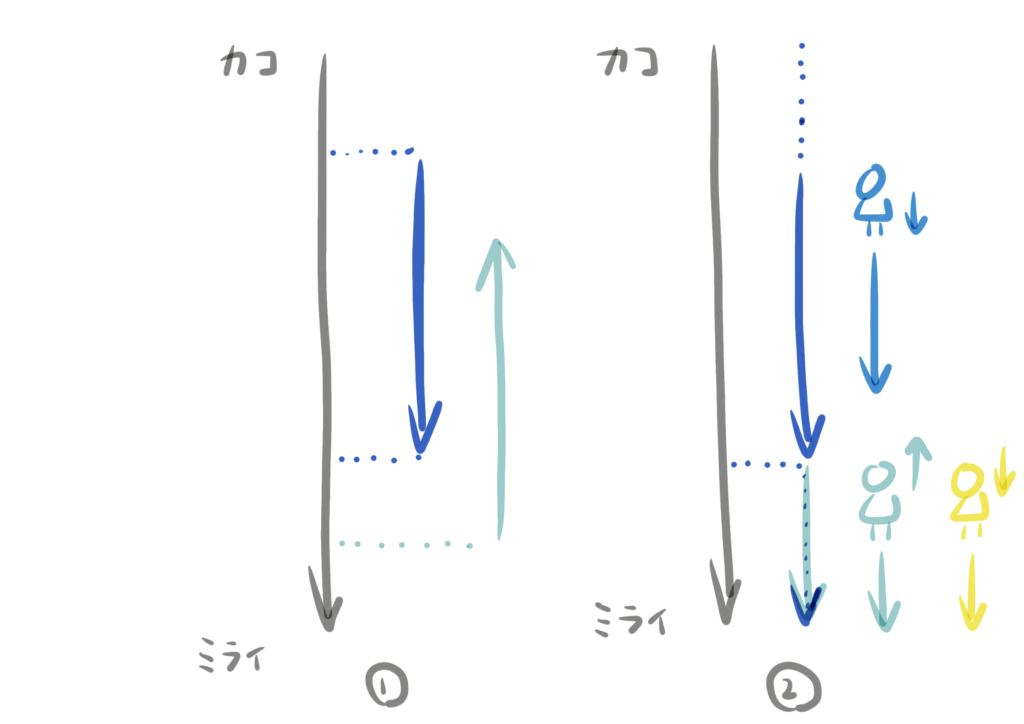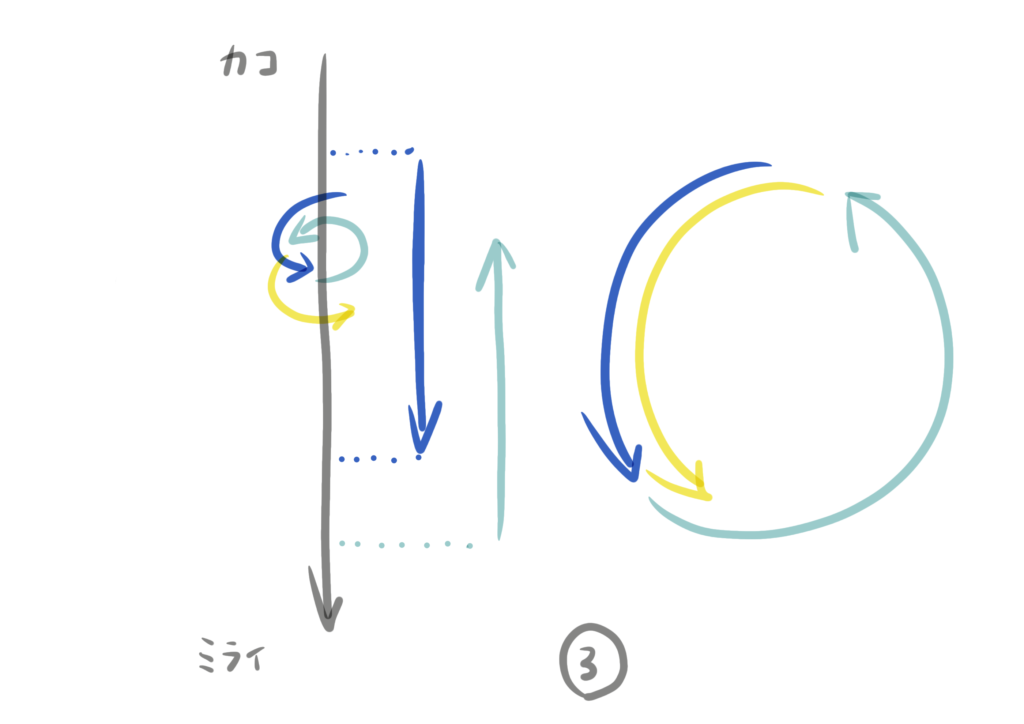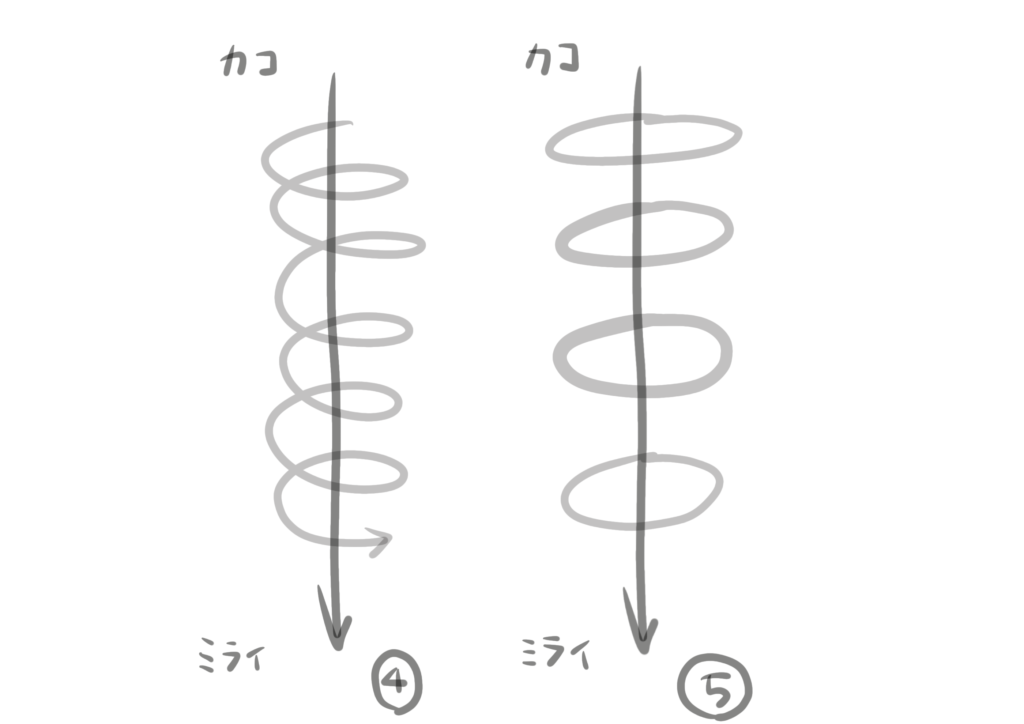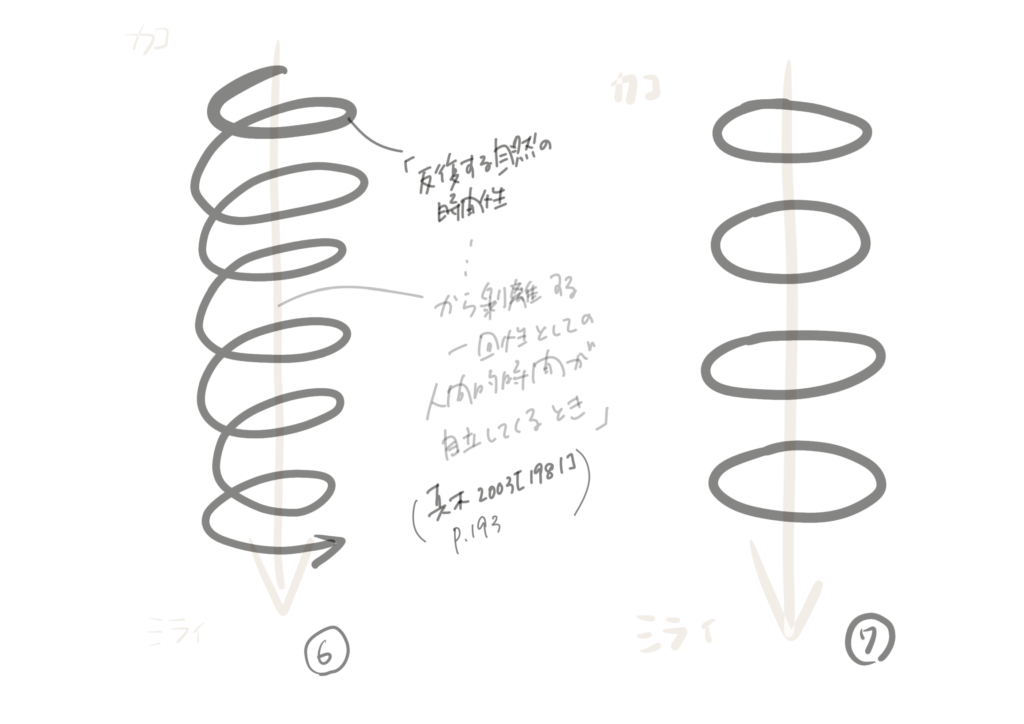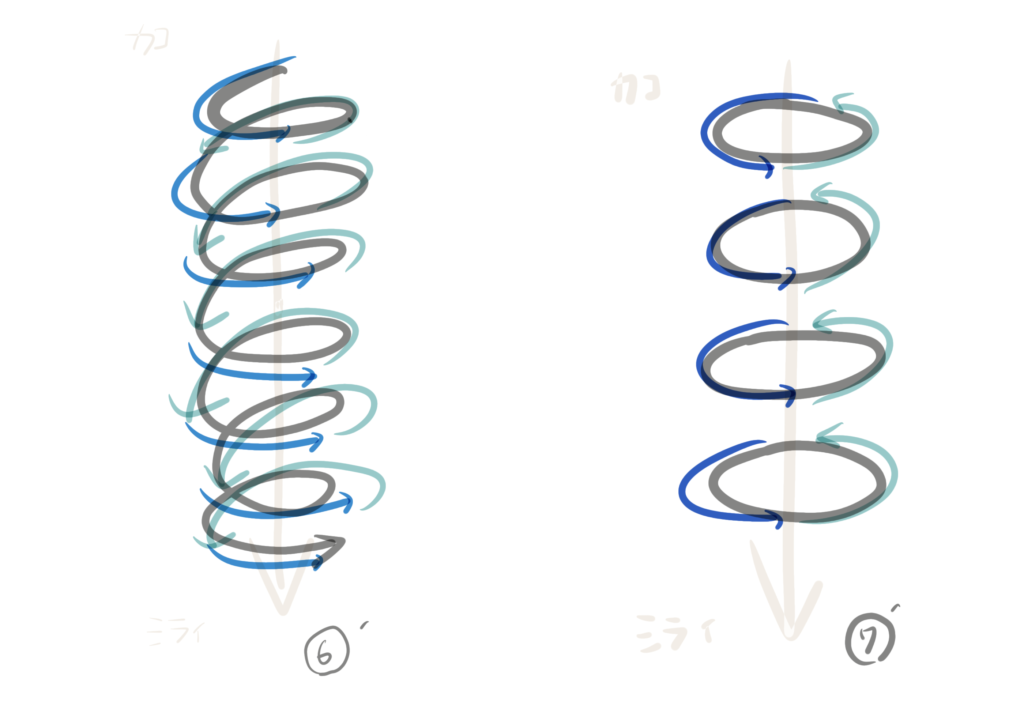2021-04-12
お風呂の中で、
いろんな話をした。
忘れたくないので、出た後にメモに吹き込んでもらい…
2回目だけど、原稿や打ち合わせは一切なしのワンテイク。
途中から、パーソナリティーになりきり。
次回も(?!)おたのしみに!
【引用元】
『おばあちゃんがおばあちゃんになった日』(長野ヒデ子さく、童心社、2015年)
【おまけ】
保育園で、こんなうたもならったとのこと…
たった10秒ほどが、すばらしい。
はてな
はてな
ほんとかな
ぐるりとまわして(頭を一周させる)
うん、そうだ
【おまけ写真】